>>396
【露わになった欲望、崩壊する静寂】
甲子園のゲート前で、一体の「裸婦像」を熱心に見つめる一人の男子生徒がいた。彼は美術品を鑑賞するかのような真剣な面持ちで、その滑らかな「大理石の肌」を指でなぞっている。
「信じられない……。これ、本当に石なのか? まるで生きているみたいに温かくて、柔らかい……。こんなに官能的な芸術、初めて見たよ」
感嘆の溜息を漏らす彼を見計らい、僕は背後から忍び寄り、彼女の背中に貼られた**『裸婦像』**のシールを、一気に剥ぎ取った。
「……えっ?」
刹那、世界が色を取り戻した。目の前の物体が「無機質な像」から「全裸の女子高生」へと書き換えられたのだ。男子生徒は驚愕に目を見開き、目の前の光景に硬直する。しかし、僕の手は止まらない。間髪入れず、彼の胸元に用意していた二枚のシールを叩きつけた。
**『性欲の塊』『変態』**
その瞬間、彼の理性は蒸発した。獣のような濁った瞳で全裸のチア部女子を見つめると、彼は周囲の目も憚らず、剥き出しの欲望のままに彼女へと襲いかかった。
「きゃあああああ! 何、なんなのこの人!」
「やめて! 誰か助けて!」
先ほどまで像だった彼女は、恐怖に顔を歪ませて悲鳴を上げる。しかし、シールを貼られた彼は止まらない。白昼堂々、甲子園の入り口で、極めて醜悪で凄惨な「青姦」が始まった。
【演出された狂気、書き換えられる常識】
「おい、何やってんだあいつ! 警察だ!」
「なんて破廉恥な……! 誰か止めて!」
周囲の観客たちが次々と異変に気付き、怒号と悲鳴が渦巻く。パニックが広がり、警備員たちがこちらへ駆け寄ってくる。このままでは僕の「カオスな鑑賞」が邪魔されてしまう。
僕はポケットから予備のシールを取り出し、絡み合う二人の背中に素早く新たなシールを叩きつけた。
**『主演俳優』『迫真の演技中』**
さらに、叫び声を上げる周囲の群衆に向かって、手当たり次第に別のシールを投げ、貼り付けていった。
**『観客役のエキストラ』**
そして、仕上げにこの空間そのものを支配するため、入り口の巨大な柱に特大のシールを貼り付けた。
**『映画の撮影風景』**
効果は絶大だった。激昂していた中年男性の動きがピタリと止まり、彼は満足げに頷いた。
「なんだ、ロケか。近頃の映画はリアリティがすごいな。俺たちもエキストラとしてしっかり映らないとな」
「本当ね、あんなに必死に叫ぶなんて、あの女優さん将来有望だわ。本物のパニックに見えるもの」
つい数秒前まで「犯罪」として糾弾していた人々は、今や目の前の凄まじい光景を「演出」だと思い込み、感心した様子でスマホを向け始めた。彼らにとって、少女の絶望的な悲鳴は「アカデミー賞級の演技」に過ぎないのだ。
【完成された地獄絵図】
さらに混乱を完璧なものにするため、僕は足元に転がっていたゴミ箱や、近くの看板にもシールを貼る。
**『特等席のソファ』『最高級のワイン』**
人々は道端の泥だらけのゴミ箱に優雅に腰を下ろし、空っぽのペットボトルを揺らしながら、目の前で繰り広げられる「性欲の塊」と「チア部女子」の絡み合いを、至高のエンターテインメントとして鑑賞し始めた。
阿鼻叫喚の叫び声は、彼らの耳には「最高の音響効果」として届き、飛び散る汗や涙は「計算された演出」として称賛される。加害者である男子生徒は、自らの名札(シール)に忠実な獣となって少女を蹂躙し続け、被害者である彼女は、誰にも助けられない絶望の中で泣き叫び続ける。
僕はその中心で、一人静かに笑っていた。
僕の目に映るのは、理性を失った獣と、絶望に染まる少女、そしてそれを「撮影の一部」として笑顔で眺める狂った観客たちの姿だ。
「これこそが、僕だけが見たかった最高の試合だ」
熱帯夜のような熱気が、さらに色濃く、僕たちを包み込んでいった。
395 名無しさん
397 名無しさん
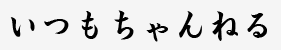


>>290
夏の甲子園、銀傘を焦がすような熱気の中で、僕だけが「真実」を知っていた。
手元には、何の変哲もない白いシールの束。しかし、これに名前を書き込んで貼れば、世界の認識は書き換えられる。その名は**「代用シール」**。僕は胸の高鳴りを抑えながら、ベンチ裏からアルプススタンドを眺めた。
1 熱狂のアルプス、静寂の予兆
アルプススタンドでは、地元の高校を応援するチアリーダーたちが、弾けるような笑顔で踊っていた。
「ゴー!ゴー!レッツゴー!」
溌剌とした掛け声、揺れるポニーテール、そして短いスカート。彼女たちは青春の象徴そのものだった。僕は油性ペンを取り出すと、シールに迷いなく、たった三文字を書き込んだ。
**『裸婦像』**
僕は人混みに紛れ、応援団の最後列に陣取った。そして、風の魔法でも使うかのように、彼女たちの背中に次々とそのシールを貼り付けていった。
2 消失した生気、剥がれ落ちる青春
効果は劇的だった。
シールを貼った瞬間、さっきまで太陽のように笑っていた彼女たちの瞳から、ふっと光が消えた。機械的に動いていた手足が止まり、チアJKたちは虚空を見つめる「石像」のような無表情へと変貌した。
やがて、彼女たちは示し合わせたかのように、一切の躊躇なく、その場にチア衣装を脱ぎ捨て始めた。ユニフォームが、アンダーウェアが、夏の風に舞い落ちる。全裸。しかし、彼女たちに恥じらいの色はない。なぜなら、彼女たちはもう「女子高生」ではなく、無機質な「裸婦像」なのだから。
「おい、どうしたんだ……? 急にみんないなくなったぞ!」
周囲の男子生徒たちが騒ぎ出した。だが、彼らの目には目の前の「全裸の少女たち」が映っていない。彼らが驚いているのは、ただ「チア衣装が床に散乱していること」と「応援団がいなくなったこと」に対してだけだった。
目の前で一糸纏わぬ姿で立ち尽くす彼女たちは、周囲にとって「そこにあるはずのない空気」あるいは「最初からあった背景」と化していた。
3 球場に佇む、美しき沈黙
全裸となった彼女たちは、一列に並んで無言のままスタンドを後にした。
出口へと向かう足取りは静謐で、感情の欠片も感じられない。僕は彼女たちの後を追い、甲子園のゲート付近へと向かった。
球場の入口付近。そこには、左右対称に並び、優雅な曲線を描いてポーズを取る彼女たちの姿があった。ある者は天を仰ぎ、ある者は物憂げに視線を落とす。肌に触れる熱風も、観客の喧騒も、今の彼女たちには届かない。
「へえ、こんなところに新しい銅像ができたのか。ずいぶん精巧だな」
「甲子園の新しいフォトスポットかな?」
来場者たちは、全裸で硬直する彼女たちの横を、何の疑問も持たずに通り過ぎていく。中には、彼女たちの白い肌を「本物の大理石」かのように叩いて確かめる者さえいたが、彼女たちは眉ひとつ動かさない。
4 カオスな世界を独り占めする
僕は、灼熱の太陽の下で「裸婦像」として永遠の沈黙を強いられた彼女たちの前で、ひとり冷たいコーラを飲み干した。
応援の声が遠くに聞こえる。
世界はいつも通り動いているように見えて、その実、僕の書いた三文字に支配されていた。
彼女たちはこのまま、夏の甲子園が終わるまで、あるいはシールが剥がれるその時まで、美しい「彫刻」として来場者を出迎え続けるのだ。
僕は、誰も見向きもしない彼女たちの「真の姿」を眺めながら、自分だけが知るこのカオスな光景に、人知れず歪な笑みを浮かべた。