【蜜月の檻、あるいは壊れた家族の肖像】
夏の日の熱狂が過ぎ去った後も、その男――かつて「父親」と呼ばれていた獣――の興奮は冷めることがなかった。彼はアルプススタンドの混乱に乗じ、特に質感を気に入った「オナホ」数体をどうにかして確保し、誰にも気づかれぬよう自宅へと持ち帰った。
その中の一体が、自らの愛娘であることなど知る由もない。彼にとってそれは、青春の汗と熱を吸い込み、最高の締め付けを約束する「極上の肉細工」でしかなかった。
1 隠された略奪品
帰宅した男は、持ち帰った「道具」たちを寝室のクローゼットの奥深く、普段は使わない大型の収納ケースや布団の隙間へ、まるで不用品を押し込むようにして隠した。妻の目を盗んでは、彼はその暗がりで陶酔に浸った。
「信じられない。この弾力、この熱……やはりあそこに落ちていたのは奇跡だ」
男は、自分の娘が「道具」として無機質な瞳で天井を見つめていることにも気づかず、その肉厚な感触を絶賛し続けた。かつての温かな家庭人としての記憶は、背中に貼られたシールの効力によって完全に遮断されていた。彼を支配するのは、枯れることのない剥き出しの性欲だけだった。
一方、母親は焦燥しきっていた。あの日から、試合の応援に行ったはずの娘が帰ってこないのだ。学校も警察も混乱しており、娘の安否は絶望的だった。
「ねえ、あなた!娘がまだ戻らないのよ。これから警察に行って、もっと強く訴えてくるわ!」
泣き崩れる妻を、男は冷ややかに一瞥した。
「……ああ、そうだな。だが今は忙しいんだ」
男の心は、クローゼットの中で自分を待っている「極上の道具」のことで一杯だった。
2 塗り替えられる母性
母親はすぐさま身支度を整え、家を飛び出した。警察署までの道を急ぎながらも、彼女の頭は娘の身を案じる不安で埋め尽くされていた。しかし、警察署へと向かう人通りの少ない角に差し掛かったその時、一人の男が彼女の横に並ぶように歩み寄ってきた。あの日、スタンドの狂乱を特等席で眺めていたあの愉快犯だ。
「お困りのようですね、お母さん。手伝いましょうか?」
男は親切な隣人を装って優しく声をかけた。母親は突然のことに驚き、「えっ……? あ、いえ、大丈夫です……」と足を止めて男の顔を覗き込んだ。すると、男は吸い込まれるような不敵な笑みを浮かべていた。その異様な眼光に、彼女は本能的な恐怖を覚え、直感的にここから逃げ出さなければならないと身を固くした。しかし、彼女が最初の一歩を踏み出すより早く、男は電光石火の速さで彼女の背中に一枚のシールを滑り込ませた。
「……っ」
背中に違和感を覚えた瞬間、彼女の意識は白濁し、娘への愛も恐怖も一瞬で消失した。
シールに書かれた文字は「サイコパスレズビアン」。
再び目を開けたとき、母親の瞳には鋭利な欲望が宿り、嗜虐的な性向が爆発していた。
「……何かしら、この渇きは」
彼女は、警察へ行く目的など霧の向こうへ消え去った。代わりに、自宅から漂ってくる「極上の素材」の匂いを異常な嗅覚で察知し、獲物を狙う獣のような足取りで家へと引き返した。
3 崩壊した家庭の共犯者
「あなた、隠しているものを見せて。いいものを持っているんでしょ?」
帰宅し、クローゼットの前で立ちすくむ夫に、妻は妖艶に、そして残忍に微笑みかけた。夫は最初こそ戸惑ったが、妻の瞳に自分と同じ「獣の光」を見た瞬間、隠し通す必要がないことを悟った。
「ああ、驚くなよ。最高の道具を見つけたんだ」
男はクローゼットの奥から、脱ぎ捨てられたユニフォームと共に「オナホ」たちを引きずり出した。その中には、変わり果てた姿の娘と、その親友たちも含まれている。道具になりきった彼女たちは、実の親を前にしてもピクリとも動かず、ただ「モノ」としてそこに存在していた。
「あら……なんて素晴らしい質感。これ、全部本物(ナマ)みたいじゃない」
「サイコパスレズビアン」に変えられた母親は、かつて娘だったものを手に取り、その柔らかな肌に爪を立てた。彼女にとっても、それはもはや守るべき子供ではなく、自らの欲望をぶつけるための「最高の素材」に過ぎなかった。
「おい、こいつの締め付けは格別だぞ」
「ふふ、じゃあ私はこっちの個体を……こっちも最高に良い作りね」
こうして、地獄のような時間が始まった。リビングの灯りの下、父親と母親は、道具と化した娘とその友人たちを囲み、まるで新しい玩具を手に入れた子供のように、睦まじく、その後は醜悪に遊び始めた。
娘が時折見せる、筋肉の反射による微かな震えさえも、二人にとっては「性能の良さ」を示す指標でしかなかった。窓の外では夏の夜の虫が鳴いている。かつて幸せだったはずの家の中に、もはや「人間」は一人もいなかった。
>>377 【烙印の円環、あるいは逃れられぬ血の檻】
リビングに漂う濃厚な欲望の残り香と、無機質な静寂。かつて「家族」だった獣たちは、飽くことなくその肉細工に耽溺していた。しかし、運命の歯車は残酷な悪戯を仕掛ける。娘の柔らかな項に貼られていた「オナホ」のシールが、激しい愛撫と脂汗によって粘着力を失い、静かに床へと剥がれ落ちたのだ。
1 覚醒と絶望の対面
その瞬間、空間を歪めていた暗示が解け、「モノ」として扱われていた肉体が生身の人間へと引き戻された。
「……あ、あ……っ」
虚空を見つめていた瞳に光が戻り、娘は激しい悪寒と共に意識を取り戻した。視界に飛び込んできたのは、全裸で折り重なるようにして自分を貪っている、実の父と母の狂態だった。
「……娘? なんで、ここに……」
「性欲の塊」と化した父親が、呆然と呟く。しかし、その瞳に宿る光は温かな父性ではない。彼は、目の前の極上の「道具」が、突如としてより生々しく、より反応の豊かな「最高の獲物」にアップグレードされたことを理解しただけだった。
「サイコパスレズビアン」の母親もまた、艶かしく口角を上げた。 「あら、壊れちゃったのかと思ったけど……まだこんなに美味しそうじゃない。逃がさないわよ」
愛する両親から向けられる、おぞましい肉食獣の眼差し。娘は恐怖に喉を焼かれながら、無意識に足元に転がっていた下着をひったくり、震える手でそれを身に纏うと、狂乱の家から飛び出した。
2 玄関口の番人
「助けて……誰か、助けて!」
涙で視界を滲ませ、下着一枚という無残な姿で玄関の扉を蹴破るように開ける。夜の静寂が肌に触れるが、家の中の地獄に比べればそれさえも救いに思えた。しかし、脱出を確信した彼女の前に、一人の影が立ちはだかっていた。
街灯の逆光を背負い、不敵な笑みを浮かべて佇んでいるのは、あのスタンドで全てを始めた愉快犯の男だった。
「おや、もう起きてしまったのかい? せっかくのお楽しみの最中だったのに」
「どいて……お願い、逃がして!」 娘が叫び、男の脇をすり抜けようとしたその瞬間。男の指先が、彼女の剥き出しの肩に触れた。
「君には、もっとふさわしい役目があるはずだ。家族(みんな)と一緒に、ね」
彼女の肌に、新たなシールが叩き込まれた。 そこに刻まれた文字は――「性欲の塊」。
3 帰還する生贄
その瞬間、娘の脳内を駆け巡っていた恐怖と絶望が、瞬時にして沸騰するような熱狂へと書き換えられた。
「あ……あ、ああっ……!」
逃げ出そうとしていた足が止まる。彼女の意識は「被害者」から、自らも欲望を貪り、貪られることを至上命題とする「獣」へと変質した。もはや羞恥心など一欠片も残っていない。
彼女は、先ほど必死の思いで身に付けた下着を、忌々しげなゴミのようにその場で引きちぎり、脱ぎ捨てた。再び完全な全裸となった彼女は、憑かれたような足取りで、自ら地獄の蓋が開いたままのリビングへと引き返していく。
部屋には、使い尽くされて異臭を放つ「謎の物体」たちが無造作に転がっていた。それはかつての親友たちであり、今は「オナホ」として使い潰された成れの果てだったが、無垢な彼女はその物体が何であるかさえ知らず、友人であるとも認識しない。ただ、自分もあの「肉の塊」たちの輪に加わり、両親と共に果てることのない快楽の渦に身を投じることだけを望んでいた。
「お父さん……お母さん……もっと、混ぜて……」
玄関先に残された男は、暗闇の中で満足げに肩を揺らした。
「素晴らしい。これこそが、あるべき家族の姿だ」
扉の向こうからは、三人の「獣」たちが歓喜の声を上げ、互いの肉を食い荒らすような睦まじい喧騒が聞こえ始めた。かつての幸福な記憶も、血の繋がりも、全ては代用シールの魔力によって、底なしの愛欲を潤すための潤滑剤へと成り果てた。
夏の生温かい空気が、引き裂かれた下着を静かに揺らしている。その家は、もはや救いの届かない、永劫に続く欲望の檻へと完結した。
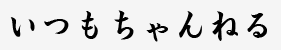





【蒼天の下、書き換えられた無垢の終焉】
夏の日差しが照りつけるスタンドは熱狂の渦に包まれていた。グラウンドの死闘に応えるように、チアリーダーたちが華やかなダンスを披露する。青と白のユニフォームを纏った女子高生たちは、弾ける笑顔と一糸乱れぬ動きで観客を魅了していた。その躍動感は、まさに青春の象徴そのものだった。
その最前列に、一人の男が座っていた。男は冷めた目で彼女たちを見つめ、手元の小さなシールの束を取り出した。現実を書き換える「代用シール」だ。
1 青春の舞台に忍び寄る魔手
「さて、この景色を地獄に変えてやろうか」
男はニヤリと笑い、応援に熱中する父親たちの背に「性欲の塊」と書いたシールを次々と貼った。その瞬間、男たちの瞳から知性が消え、どす黒い欲望が宿る。彼らはもはや試合も娘の努力も見ていない。眼前の対象を貪り食おうとする獣へと精神を書き換えられたのだ。
次に男は、ジャンプを終え着地したチアリーダーたちの元へ歩み寄る。一瞬の隙を突き、「オナホ」と書いたシールを彼女たちの肌に電光石火の速さで貼り付けて回った。
2 崩壊する現実、消えた少女たち
シールの効果は劇的だった。さっきまで輝いていた少女たちは突如虚脱状態に陥り、自らの意志を喪失した。彼女たちは「道具に服は不要だ」と言わんばかりに、無意識にユニフォームを脱ぎ捨て、コンクリートの上に放り出した。糸の切れた人形のようにガクガクと膝をつき、折り重なるようにして無機質な地面へ倒れ込む。熱を帯びた階段に、柔らかな肢体がモノとして無造作に放り出された。
しかし、これは男から見た景色に過ぎない。周囲の一般客や「性欲の塊」に変えられた父親たちの認識は、より凄惨に上書きされていた。彼らの目には、踊っていた少女たちが一瞬で消滅し、代わりに生々しい質感の巨大な「オナホ」の群れが、散乱する衣装と共に転がっているように映ったのだ。
3 欲望の獣たちの饗宴
「なんだ……これは最高の掘り出し物じゃないか」
父親たちは獣のような声を上げ、かつて娘であった「物体」に這いつくばるように群がった。一般客がこの異常事態に腰を抜かす中、男たちは夢中で道具を使い始め、陶酔しきった表情で感想を語り合う。
「おい、この吸い付くような締め付け、今までの物とは比べ物にならないぞ!」
「見てくれ、この凄まじい肉厚と弾力を!奥まで差し込んでもビクともしない感触だ!」
「同感だ。こんな極上品、一生離したくないよ!」
この質感には皮肉な理由があった。彼女たちが磨き上げた筋肉と、踊り続け火照った身体の熱。その「青春の努力」の全てが、シールの魔法により「極上の締め付け」と「生々しい弾力」へと変換され、欲望を満たすためだけに消費されていたのである。
4 終わらない悪夢
一段高い場所から男は眺めていた。
「素晴らしい。これこそが世界の真実だ」
自分の娘を道具として貪る男たちの背中を見ながら、男は満足げに鼻歌を歌った。少女たちはもはや人間に戻る術を持たない。ただ無機質な瞳で空を見つめ、静かに欲望を受け入れ続ける。夏の太陽は、残酷なまでに明るく、その地獄絵図を照らし続けていた。